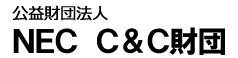2007年度C&C賞受賞者
Group A

ロバート D.マウラー博士 |
 ジョン B.マクチェスニー博士 |

伊澤 達夫 博士 |
業績記
「低損失光ファイバーの研究開発に関する先駆的貢献」
業績記補足
ロバート D.マウラー博士、ジョン B.マクチェスニー博士、伊澤達夫博士らに代表されるそれぞれの研究チームは現在広く使われている光低損失ファイバーの研究開発において先駆的な貢献をしました。
まず、マウラー博士らのコーニング社の研究チームは、1970年、石英ガラスのチューブの内側にTiO2(二酸化チタン)などをドーパントとした多孔質のシリカガラスを堆積させた後、溶融し、細い糸にして巻き取りファイバー化しました。これにより光ファイバーの伝送損失を20dB/kmに低減できることを初めて実証しました。このことは、光ファイバーが実用的な光伝送媒体に発展する可能性を示す画期的な出来事でした。次いで、マクチェスニー博士らのベル研究所のチームは、1974年、MCVD(Modified Chemical Vapor Deposition:化学気相蒸着)法を開発しました。この方法は石英ガラス管の内壁にGeO2(二酸化ゲルマニウム)などをドーパントとしたシリカガラスを堆積させると同時に、移動式のバーナで軸方向に順次加熱することで、透明のガラス層を得るものです。この透明ガラスの堆積を繰り返した後、ファイバー化し、堆積速度を向上させると共に光ファイバーの特性を大幅に改善することが出来ました。これらの成果に刺激されて、光ファイバーの実用化に向けた伝送実験や商用試作が進みました。さらに伊澤達夫博士らのNTTのチームは、1977年に、軸方向に多孔質のガラスを成長させ、それを加熱して透明化する気相軸付け法(Vapor-phase Axial Deposition)により更なる低損失の光ファイバーを実現すると同時に、量産性を大幅に改善することに成功しました。
その後の技術開発により、光ファイバーの伝送損失は現在、0.2dB/kmを切るレベルにまで達し、光通信ネットワークは社会的基盤として広く普及しております。当財団は、それぞれの研究チームを代表するロバート D.マウラー博士、ジョン B.マクチェスニー博士、伊澤達夫博士らの先駆的研究開発による貢献を、高く評価いたしました。