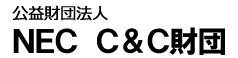2014年度C&C賞受賞者
Group B

ヤン・ウッデンフェルト 博士 エリクソン、ソニー シニア・アドバイザー |

アーウィン・マーク・ジェイコブス 博士 クアルコム 創業者会長、名誉CEO |

安達 文幸 教授 東北大学 大学院工学研究科 通信工学専攻 教授 |
業績記
デジタル移動通信システムの開発と実用化に関わる主導的・先導的貢献
業績記補足
移動通信サービスは、1970年代の終わりから1980年代の初めにかけて、自動車の音声通信を中心としたアナログ方式による第1世代(1G)と呼ばれるサービスが始まりました。1990年代になると、システムコストの低減とともに、メッセージングサービス等のインターネットを利用した新たなサービスの導入を目的として、第2世代のデジタルシステムが登場し、広く一般ユーザに普及しました。さらに2000年代に入ると、より高速な第3世代(3G)の方式が登場し、マルチメディア通信等の高度なデータ通信サービスを実現しました。
これらの技術やサービスの進歩に、新興国等での通信利用への要望拡大も加わり、移動通信サービスは爆発的な普及を見せ、今日では世界的な社会インフラとして無くてはならないものとなっています。
ヤン・ウッデンフェルト博士、アーウィン・マーク・ジェイコブス博士、安達文幸教授は、今日の移動通信サービスの繁栄の基礎を築いたデジタル移動通信システムの技術開発と標準化において、非常に重要な役割を果たしました。3名は、欧州、北米、日本の各地域の貢献者の代表として、また各世代の技術の貢献者の代表として、顕著な功績と卓越したリーダーシップを示すとともに、各地域に限定されることなくグローバルな活躍をされてきました。
ウッデンフェルト博士は、第2世代の移動通信システムから第3・第4世代の移動通信システムの開発と標準化に主導的な貢献を果たしました。特に、第2世代のグローバル標準システムである、GSMの開発と標準化において主導的な貢献を行った技術者の代表になります。同氏のグループは、GSMの検討過程において、従来移動無線環境では困難であった時分割マルチアクセス(TDMA)方式での高速伝送を可能にする適応等化技術の確立に貢献し、多くの技術者と協力してTDMAをベースに初めてのデジタル移動通信システムを完成させました。
また同氏は、移動機補助ハンドオーバー(MAHO: Mobile Assisted Hand Over)や周波数ホッピング等の多くの革新的技術のGSMへの導入においても重要な役割を果たしました。これらの革新的技術は加入者容量の増加、基地局コストの低減に大きく寄与し、マイクロセル化への道を開きました。GSMでは、これらの多くのシステム技術が実現され、今日の移動通信インフラの基盤となっています。
さらに同氏は、第3世代の移動通信システムの開発とグローバル標準化にも尽力しています。1990年代初めに欧州研究プログラムにおいて、第3世代の移動通信システムへのW-CDMAの採用を提案し、W-CDMAをGSMコアネットワークの追加拡張とし、GSMとW-CDMAのデュアルモード端末を使用する基本的な3Gアーキテクチャの導入も行いました。このアーキテクチャは、グローバルな3G標準の基本となり、ネットワーク構築コストの低減実現によって成功を収めています。
ジェイコブス博士は、デジタル移動通信システムのための符号分割マルチアクセス(CDMA)技術の開発と標準化、実用化に主導的貢献を果たしました。CDMAは、最初は第2世代の携帯電話標準の一つとして導入されましたが、その後全ての第3世代の携帯電話ネットワークの基盤技術としても選ばれ、現在では、30億人もの携帯電話加入者に利用されています。
CDMAは、移動通信の音声と広帯域データ通信に対する無線スペクトルの極めて効率的な使用を可能にしました。この実現のため、同氏と同氏のグループは、マルチレベルの通信電力制御、ソフトハンドオフ、共通パイロット、そしてマルチパス信号補正を提供するレイク受信機などの様々な革新的な技術を導入しました。さらに同氏は、これらの機能を実現する集積回路の開発とともに、今日のような小型で多機能なモバイル機器の実現を可能にするシステムオンチップと呼ぶ集積回路への拡張も指導しています。
CDMA技術は、1993年にIS-95(cdmaOne)システムとして標準化され、その後パケットデータを主な対象とした拡張を加え、最初の第2.5世代のシステムとして実用化されました。これらの拡張技術は、EVDO (Evolution data optimized)やHSPA (High-speed packet access) として、第3世代の中でも広く利用されている移動通信システムの広帯域化に進展しています。
安達教授は、今日グローバルに利用されている第3世代システムに採用されている広帯域CDMA(W-CDMA)技術の研究開発において、主導的な貢献を果たしました。同氏は、第3世代の移動通信用の無線アクセス技術の開発の当初からCDMA技術に着目し、移動通信の将来を見据えると高速広帯域のマルチメディア通信を柔軟に提供できる広帯域CDMA(W-CDMA)技術を開発すべきであること、そして柔軟性に優れたシステム展開を可能とする非同期基地局システムにすべきであることを主張し、W-CDMA技術の開発を世界の先頭に立って推し進めてきました。
同氏とそのグループはターボ符号化、干渉キャンセラなど技術の研究において学術レベルで貢献するとともに、異なる伝送速度の通信を効果的に行う直交可変拡散率(OVSF)符号の考案やパイロットを用いる同期検波受信方式や非同期システム環境下でも可能な高速セル探索方式の開発、等によって、従来のCDMA技術を広帯域化し高速移動マルチメディア通信を可能としました。同氏のグループの研究成果を基に開発されたW-CDMA技術は、第3世代のマルチメディア移動通信システムのための無線アクセス方式として標準化されています。
今日、デジタル移動通信システムは、スマートフォンやタブレットの発展や普及等に伴い、インターネットサービスやソーシャルサービス、金融や健康管理・医療に至るまで、様々なサービス分野で欠く事のできない重要な社会インフラとなっています。現在、移動通信システムは、より広範なマルチメディアサービスを提供する第4世代のシステムへの移行が進んでおり、さらには第5世代のシステムの検討も開始されていますが、これらの基盤ともなっている移動通信のシステム技術に関する3氏の業績は極めて顕著であり、さらには移動通信のみならず情報通信全般の発展にも大きく貢献するものとして、C&C賞に相応しい業績と言えます。