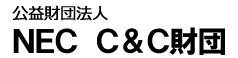2024年度C&C賞受賞者
Group A
.jpg)
秋葉 重幸 博士 元(株)KDDI研究所 |
(1400x1050).jpg)
鈴木 正敏 博士 公立千歳科学技術大学 |
.jpg)
森田 逸郎 博士 早稲田大学 理工学術院 教授 |
業績記
大容量波長多重光海底ケーブルシステム開発・実用化への貢献
業績説明
19世紀後半、海底ケーブルの敷設により1回線の電信から国際通信が始まりました。電話にも使える同軸ケーブルが登場し、回線容量は拡大します。しかし、1970~1980年代は回線容量が大きい衛星通信が主流でした。1980年代に入り、光ファイバ及び半導体レーザが実用化されると、光ファイバの低損失性と広帯域性を活かして、海底ケーブルの中継器数を減らしつつ、大容量伝送が可能となり、通信コストを低減できることから、光海底ケーブルが使用されるようになります。太平洋横断ケーブルでは、1989年、光ファイバを使用したTPC-3 (ファイバ当たり容量:280Mbps)、1992年にTPC-4 (同:560Mbps)、1995年には、光増幅中継伝送方式を導入して伝送容量を大幅に増やしたTPC-5 (同:5Gbps)が運用開始されました。しかし、光ファイバを伝搬する光波の速さは波長によって異なる現象(波長分散という)と光ファイバの非線形性によって、波長多重信号波形を歪ませるため、1万kmに及ぶ光海底ケーブルシステムの大容量化を大きく阻害していました。光海底ケーブルシステムの大容量化、特に、波長多重方式の光海底ケーブルシステムを刷新し、急速に拡大するインターネットの通信需要を支えたのが、秋葉博士、鈴木博士、森田博士をはじめとするKDDIの技術者です。
秋葉博士は、光ファイバの損失が最小となる波長1.5μm帯のシステム開発に向けて研究開発を開始、1979年に、1.5μm帯半導体レーザの室温連続発振に成功、次いで、単一モードで動作する分布帰還型レーザの開発を主導し、TPC-4の実現に貢献しました。また、TPC-5の中核技術となる高信頼光増幅中継器の研究を主導し、その実用化にも大きく貢献しました。さらに、同博士は、光ファイバの非線形性を抑制する大口径光ファイバと、波長980nmの励起レーザを用いて低雑音化した光増幅器を組み合わせるシステムを提唱し、一波長当たり10Gbpsの波長多重光海底ケーブルシステム開発の統括責任者として指導的役割を果たしました。
鈴木博士は、光海底ケーブルシステムの高速化に必要となる高速光変調器の研究開発を開始、半導体吸収型高速光変調器、次いで、1987年に半導体光変調と分布帰還型レーザの一体集積化に世界で初めて成功し、Japan-USケーブルなどの高速信号を用いる大容量波長多重光海底ケーブルの実現に貢献しました。また、鈴木博士と森田博士は、光ファイバの非線形性と波長分散による信号波形の歪を補償する方式として、波長分散が正と負の光ファイバを周期的に交互に配置する光ファイバ伝送路において、ガウス型RZ(リターン・ツー・ゼロ)光パルス信号が周期的に波形を変えながら一定区間ごとに同一形状を保ちつつ、安定に1万㎞以上の長距離を伝搬可能とする新しい伝送方式を考案・実証しました。本方式は、光ソリトン伝送固有のタイミングジッタ(光信号の到着時間の揺らぎ)による伝送距離の制限の問題も解決し、40Gbpsの高速光信号の伝送距離を従来の10倍以上の1万km以上に延伸可能であることを世界で初めて実証しました。更に、波長多重用光ファイバを用いて10Gbpsで16波から100波長多重までの大洋横断伝送にも世界で初めて成功しました。本技術は、非線形性を有する波長多重用の光ファイバを含む分散補償光ファイバ伝送システムの高品質で安定な信号伝送を可能とする分散マネージドソリトン伝送方式として広く普及し、長距離光ファイバ伝送システムの基礎技術となりました。
3氏が開発した技術は、波長多重光海底ケーブルの必須技術となり、1999年から2016年までに、太平洋横断(PC-1:1999年、Japan-US:2001年)、大西洋横断(TAT-14:2001年)、および、アジア域(C2C:2001年、EAC:2002年)の光海底ケーブルや1Tbpsクラスの太平洋横断光海底ケーブル(TGN-Pacific:2003年、UNITY:2010年)など、総システム長20万6千kmに及ぶ多くの光海底ケーブルへ適用されました。インターネットやスマートフォンの普及により急速に拡大した通信トラヒックを支えるグローバルブロードバンド基盤の実現に多大な貢献をしました。
デジタル・コヒーレント技術を用いた光海底ケーブル(FASTER:2016年)では容量が10Tbpsまで拡大されていますが、既に光ファイバの非線形性の影響による光入力パワーの制限による伝送限界(非線形シャノンリミット)に近づいています。鈴木博士と森田博士は伝送限界を打破する将来技術として光空間多重技術の研究を主導し、新規のマルチコア光ファイバによる140Tbpsの大洋横断システムの実現可能性も実証しています。
秋葉博士、鈴木博士、森田博士は、長距離光海底ケーブルの大容量化、特に、光非線形制御による大容量化技術の研究開発に先導的に取り組み、太平洋・大西洋横断大容量光海底ケーブルへ適用する主導的役割を果たしました。光海底ケーブルは、国際通信の約99%を担う大動脈です。これらの業績は、学術的・産業的な波及効果が極めて大きく、世界的に顕著な業績であり、C&C分野での社会的貢献度が大きく、C&C賞にふさわしいと考えます。