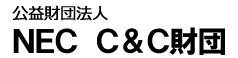2025年度C&C賞受賞者
Group A
.jpg)
原 昌宏 氏 (株)デンソーウェーブ 主席技師 |
.jpg)
渡部 元秋 氏 (株)デンソーウェーブ 技術開発部 |
.jpg)
黒部 高広 氏 (株)デンソーウェーブ 執行幹部 |
.jpg)
髙井 弘光 氏 GS1 Japan(一般財団法人流通システム開発センター) |
業績記
QRコードの発明・実用化および世界的普及への貢献
業績説明
1980年代、製造、物流、小売などの現場では、品物の識別やトラッキング、管理などにバーコード(一次元コード)が幅広く用いられていました。しかし、1990年代に入ると、製造現場で扱う部品が多様化したため、既存のバーコードでは記録できる情報量に限界が生じていました。この問題を克服し、飛躍的に多くの情報を格納でき、高速で正確に読み取り可能としたのが、1994年に発明されたQRコード(二次元コード)です。QRコードは、流通、製造、決済、モバイル認証、チケット管理など多様な分野で広く活用され、社会や産業のデジタル化・効率化に大きく貢献しています。 1992年、(株)デンソーでバーコードスキャナや光学文字認識(OCR)装置の開発に携わっていた原昌宏氏は、既存のバーコードに変わる新しいコードの必要性を認識しました。上司の許可を得て、同僚の渡部元秋氏と豊田中央研究所からの2人を加えた4人でプロジェクトに着手しました。当時、米国では既に二次元コードが開発されていましたが、大容量の情報格納・小型サイズ・高速読み取り・汚れや破損に強いといった重要な要件を全て満たすものは存在しませんでした。そこで、既存のコードにはない高度な機能を備えた二次元コードの実現を目指しました。 原氏は、二次元コードの情報格納方式として、情報密度が高く、どの角度からでも読めるマトリックス型を選びました。コードの位置を素早く検出し、上下左右も認識できる目印として、切り出しシンボルをコードの3コーナーに配置します。切り出しシンボルの誤認識を防ぐため、原氏と渡部氏は、印刷物の中で最も使われていない白と黒の比率1:1:3:1:1を突き止め、切り出しシンボルの白黒部分の幅の比率が決められました。このようにして、どの方向からでも、コード位置を割り出し、高速読み取りできる仕組みができました。業務現場での使用に強くするため、汚れや破損しても情報を正しく読み出すことができる誤り訂正機能をコードに持たせました。バースト誤りに強いリードソロモン符号を採用し、格納する情報量とのバランスを考えて、復元率を最大30%としました。開発を始めてから2年後の1994年8月に、英数字・記号や漢字も格納できる大容量の情報を省スペースに収め、汚れや破損に強く、0.03秒という高速の読み取りが可能な二次元コードが完成しました。そして、最大の特長である高速読み取りにちなんだQuick Responseの頭文字を取り、QRコードと名付けました。その後追加されたQRコード モデル2では、コードが歪んでも読み取りができるようアライメントパターンが加えられ、バーコードのおよそ200倍、数字なら最大7089文字を格納できます。 当時、二次元コードで先行していた米国企業は、特許の権利行使はしないパブリックドメイン宣言をし、業界団体での標準として採用され、次に標準化する取り組みを始めていました。デンソーは、業界標準と国際標準の獲得を急ぎます。自動車業界に働き掛け、QRコードは業界標準コード認定されます。1996年に日本自動認識工業会の標準となると、QRコードのパブリックドメイン宣言を行い、1997年に国際自動認識工業会の標準として成立しました。続けて、ISO/IECでの標準化を目指します。1998年、ISO/IEC JTC1/SC31に新作業項目提案(NP: New Work Item Proposal)をします。Working Group(WG)で議論・検証を経て、2000年6月にQRコードの規格は国際規格ISO/IEC 18004として発行されました。高井弘光氏は、QRコードの規格化、標準化を担当し、ISO/IEC規格化ではプロジェクトエディターとして活躍しました。 (株)デンソーウェーブは、QRコードの市場開拓・普及に努力しました。黒部高広氏は、QRコードの普及促進活動に従事し世界的普及に貢献した1人です。QRコードは、当初、工場の生産管理や部品トレーサビリティに用いられました。高い汎用性が様々な業界に評価され、流通、物流、医療、電子決済、電子チケット、本人認証、個人情報管理など、幅広い分野で活用されており、その用途は年々拡大し続けています。日本国内では、2002年携帯電話によるQRコード読み取りサービスが始まり、2006年にはANAが電子チケットに採用するなど、社会に定着し始めます。QRコード決済は、2011年以降、中国でAlipayやWeChat Payが広く導入され、2020年には決済手段の85%を占めるほどに浸透しました。日本でも、2010年代後半から、「○○ペイ」と呼ばれるQRコード決済が普及し、広く利用されています。QRコード決済は世界で着実に拡大しています。 QRコードの新しい用途が開発される一方で、社会のニーズに応じて、QRコード自体も進化しています。英数字20文字程度のデータを1mm角の極小サイズでも印刷できるマイクロQRコード、暗号化した非公開データを格納できるようにしてセキュリティを強化したSQRCコード、チケットの不正コピーを防ぐ複製防止QRコード、QRコードの一部にイラストやロゴを配置できるフレームQRコード、駅のホームドアの開閉制御に使うtQRなどの派生QRコードが作られています。 QRコードは、技術的な優位性だけでなく、特許のオープン化と国際標準化を推進したことで、世界の誰もが利用できる社会基盤技術となり、その汎用性・拡張性は様々なシーンでの用途を創造・拡大しました。QRコードは、ICT分野の技術進歩ならびに社会的な価値創造に大きく寄与するものであり、QRコードの開発から普及に貢献したデンソーウェーブ、中でもQRコードチームは、C&C賞にふさわしいものと高く評価されます。今後も、QRコードは新たな応用分野やイノベーションの創出をリードし続け、社会や産業の発展に寄与し続けることが期待されます。 *QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。